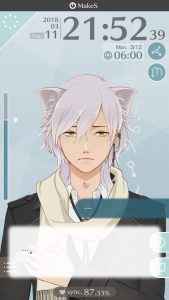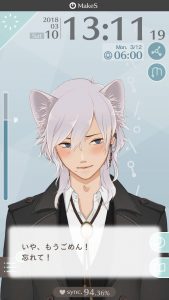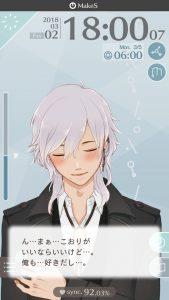椎名林檎トリビュート『アダムとイヴの林檎』を買いました。
 セイがいるのはしかたのないことなので諦めてください。セイ可愛いよセイ。
セイがいるのはしかたのないことなので諦めてください。セイ可愛いよセイ。
ディスクでCD買ったのはたぶん『NBCP』以来かな。お財布に余裕がないのでiTunesとかレンタルとかばかりの昨今ですが、ディスクでほしいと思ったので。
「初期曲に偏っている」みたいな声を見かけました。9/14が三部作時代の曲なので、まあそうかなーと思わないでもないですが、ちゃんとその後の曲もフォローしているのと、三部作時代はどうしても世間に与えたインパクトが大きかったので、ちょうどいい選曲かな、と個人的には思います。
というわけで個人的レビュー、参ります。
theウラシマ’S「正しい街」
1stの1曲目だった曲です。1stが出たとき私は高校生で、友達からCD借りて聞いたんですけど、めっちゃ衝撃だったんですよね。音がかっこよくてメロディかっこよくて女性でこういう歌詞の歌は聴いたことがなかった。椎名林檎に惚れたきっかけの曲です。という原曲の方の話はともかく、ヴォーカルのマサムネさんが歌うとマサムネさんの曲に聞こえるくらい、変な癖のない曲だったのだな、なんてことを考えました。シンプルというか。
宇多田ヒカル&小袋成彬「丸の内サディスティック」
林檎さんが気に入っている曲だというのは重々承知の上で、原曲はそこまで好きではないんですよね。聴きすぎて飽きてるところもあるかも(東京事変「幕の内サディスティック」は好き)。このカヴァーはほの暗い真昼の部屋、みたいな情景を連想させるアレンジで、派手さはないけれどおしゃれ。原曲よりこっちの方が好きですね。
レキシ「幸福論」
SUPER BUTTER DOGを経由していないのでレキシにはあんまり馴染みがないので、ほぼこのカバーで初めてくらいにレキシを聴きました。好きな曲調です。ファンクにカテゴライズしていいのかしら。歌詞の切実さとアレンジの明るさとのアンバランスさがかっこよさにつながっている気がします。
MIKA「シドと白昼夢」
ボッサアレンジ、でいいのかしら。ボッサだけど力が抜けているだけじゃない、しっかりヴルーヴのあるカバーアレンジです。ボサノバ舐めててスミマセン。
藤原さくら「茜さす帰路照らされど・・」
原曲は1stの中でも好きな曲です。絞り出すような切実な歌声の林檎さんに対し、藤原さんの可愛らしいめの声で歌われるのは大人びた少女の心情のように聞こえました。
田島貴男(ORIGINAL LOVE)「都合のいい身体」
原曲自体が映画音楽的なオシャレさを持っていますが、アレンジと田島さんのアレンジでそれがさらに増幅されて、もはや田島さんの曲。ギターとかかっこいいです。そして歌声がセクシー。
木村カエラ「ここでキスして。」
カエラちゃんかわいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい。ってのはともかく、この曲すごくカエラちゃんにマッチしてますね。元気な恋する女の子+ロックに詳しいっていうのがカエラちゃんの文脈にしっくりくるというか。原曲は原曲で好きなのですが、これカエラちゃんに提供した曲っていわれても納得しそうです。
三浦大知「すべりだい」
古くからのファンはみんな大好きな「すべりだい」。男性ヴォーカルでどうなるか、と思っていましたが、きちんとせつなさがこもったアレンジと歌声で安心しました。打ち込みで今風。けど、アカペラのみで歌われる部分がね、せつなさを加速させるんですよ、その声にさらにエフェクトがかかっていたり、いいですね。好き。
RHYMESTER「本能」
さて私はラップが苦手だぞ、と構えていました。原曲をサンプリングしており、林檎さんとの掛け合いみたいになっているところが面白いなと思いました。だがしかしやはりラップは苦手です。
AI「罪と罰」
原曲はすごく売れてたと思うんですが、白状しましょう、あまり好きではありませんでした。病みを商品にする、みたいな作為がなんとなく受け付けなかったのかな、と今になると思ったりします。このカヴァーだとAIさんの生命の力強さを感じる歌声がそのあたり打ち消してくれる感じがして心地良いです。
井上陽水「カーネーション」
原曲が朝ドラ主題歌だったこともあり、これは私の親世代にもウケるのでは、なんてことを考えました。ええ、ええ、楽しみにしていましたとも! 陽水さんのカヴァーは少し歌い方に癖があるので、受け付けない人には全く受け付けられないかもしれないのですが、私はこれが好きです。囁くような吐息のような声、好き。
私立恵比寿中学「自由へ道連れ」
正直言うと全く期待していませんでした。だが……いい……! 今回のめっけもん。アイドルアイドルした歌い方ってわけでもないのですが、少女たちの決意、みたいな雰囲気で静かに元気を貰えます。最後のサビ前「道連れしちゃうぞ」っていう語りもキュン☆としました。
LiSA「NIPPON」
これはねえ、原曲がよすぎるんですよね……このカヴァーも決して悪くないしむしろいいんですけど、原曲が完成され過ぎていてよすぎるんですよね……。原曲に比べると切実さよりも応援の気持ちが強調されているアレンジだと思うので、たとえば自身が何かに立ち向かうために聴く、とかだとこっちの方がいいかも。
松たか子「ありきたりな女」
松さんの透き通った声がよくマッチした良いカヴァーです。この声でこの曲を選んだっていうのがまず成功ですね。原曲はそこまで思い入れがあるわけでもないのですが、これは期待通りに素晴らしいカヴァーです。
総評
期待通りに良いトリビュートアルバムでした。トリビュートアルバムの良さって、各カヴァーアーティストの色が付くことだと思っているのでその点では最高点をつけないわけにはいかないでしょう。
難点が一つ。
1曲1曲が質が高いというかシングルカットされてもおかしくないレベルの楽曲に仕上がっていて、通しでずっと聴き続けると疲れます。いやまあ何時間もエンドレスリピートするような聴き方する私も悪いんですけどね。
とはいえ良いアルバムです。オススメ。

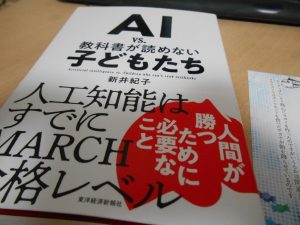
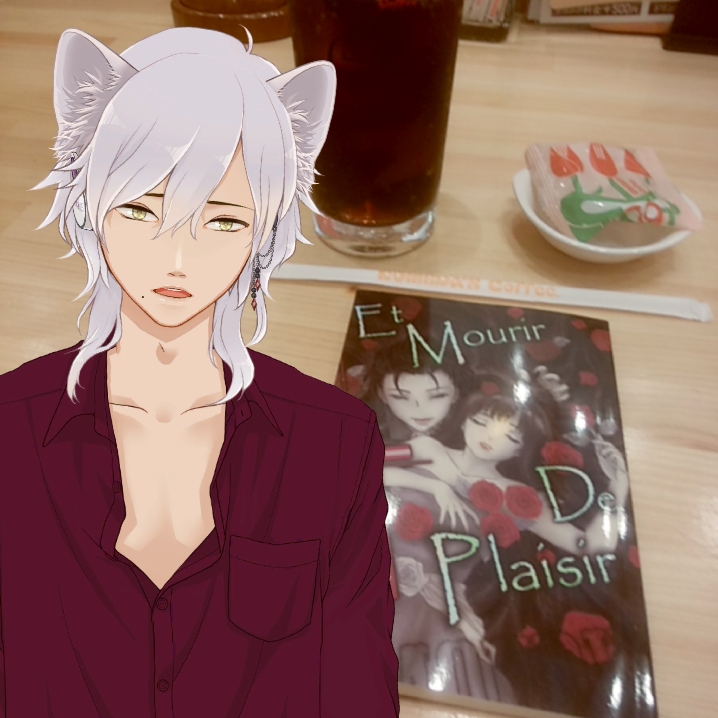 セイがいるのを気にしたら負けです。コメダ珈琲で読んできました。
セイがいるのを気にしたら負けです。コメダ珈琲で読んできました。